- 今、国立競技場の名前が変わるのはなぜか知りたい。
- 改名で何が良くなるのか、自分たちの観戦体験はどう変わるのか気になる。
- 正式名称は残るのか、いつから変わるのかも知りたい。
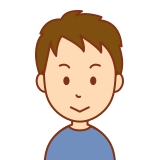
この記事では、国立競技場が改名される背景とメリットを解説します。読み終えると「なぜ名前を変えるのか」「観客や競技団体にとっての利点は何か」「いつからどう変わるのか」が分かります。
国立競技場とは

国立競技場は、東京2020大会のメイン会場として知られる日本の“スポーツの聖地”です。
陸上、サッカー、ラグビーなど多くの国際・国内大会の舞台となり、音楽イベントも行われます。
2025年4月からは民間主導の運営体制に移り、ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント(JNSE)が運営の中心を担います。
この流れの中で、2026年1月から呼称を「MUFGスタジアム」に変更して運営される予定です。
なお、正式名称はこれまでどおり「国立競技場」です。
MUFGスタジアムに改名される理由・メリットは?

安定的な財源を確保できるからです。
ネーミングライツ(命名権)により、スタジアムに継続的な収入が生まれます。
収入は設備更新やサービス向上の投資に回せるため、スタジアム運営の安定化につながります。
報道では契約は5年間で年約20億円規模とされ、国内でも最高水準の規模と見られます。
観客体験をアップデートできるからです。
デジタル技術やICTの導入が加速し、通信環境、キャッシュレス、混雑緩和の導線設計などが強化されます。
ホスピタリティエリアや飲食の刷新、スイートルームの拡充など、快適性と選択肢が増えます。
結果として、家族連れや初めて観戦する人にも優しい“未来型スタジアム”に進化します。
イベント誘致と稼働率向上に役立つからです。
大型スポーツだけでなく、音楽や文化イベントも積極的に招致し、年間の稼働日数を増やす計画です。
稼働が増えると収益も増え、さらなる投資と改善の好循環が生まれます。
首都のシンボル会場として、世界的な興行や国際大会の開催準備もしやすくなります。
公共性を保ちながら社会価値を高めるためです。
改名は商業化だけが目的ではありません。
次世代育成、地域連携、文化継承、環境配慮など、社会課題の解決に取り組むためのパートナーシップが組まれます。
銀行グループのネットワークや知見を活かし、教育・金融リテラシーの機会づくり、スタートアップ支援なども展開されます。
国際発信力とブランド力を高めるためです。
世界的な企業と連携することで、海外への情報発信や協賛の輪が広がります。
結果として、日本のスポーツ・エンタメの魅力を世界に届けやすくなり、国際大会やツアーイベントの誘致にもプラスです。
競技の“中立性”にも配慮されるからです。
国際大会や競技団体の規定(クリーンスタジアムなど)がある場合は、呼称を「国立競技場」として運用します。
つまり、商業名を使い分けつつ、競技の公平性や公共性は守られます。
いつから、どのくらいの期間?
新たな呼称の運用開始は2026年1月からの予定です。
契約期間は5年間で、2030年12月までの見通しです。
この期間に合わせて、設備や運営の刷新プロジェクト「KOKURITSU NEXT」も段階的に進みます。
まとめ
国立競技場の改名は、ただの名前変更ではありません。
安定した財源の確保、観客体験の向上、イベント誘致の強化、そして社会的な価値創出という大きな目的があります。
正式名称「国立競技場」は残しつつ、呼称としての「MUFGスタジアム」を活用することで、公共性と収益性の両立を図ります。
2026年からの5年間で“未来型スタジアム”へ進化する計画です。
私たち観客にとっては、アクセス、快適性、楽しみ方の選択肢が広がることが最大のメリットです。
動きがあれば本記事も随時アップデートしていきます。

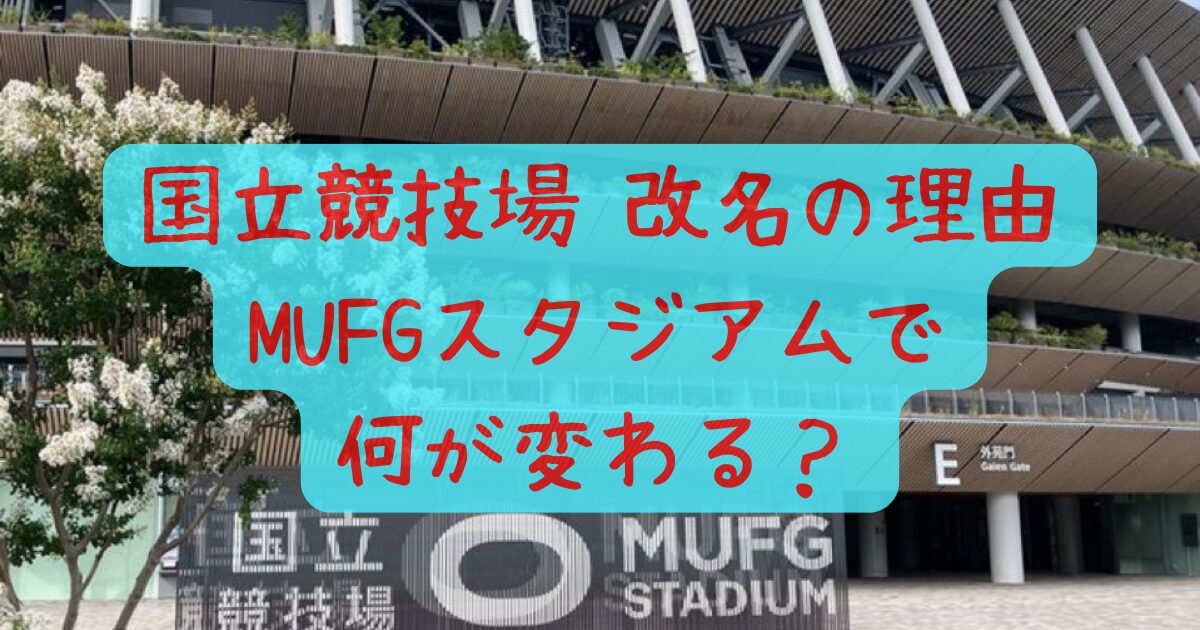


コメント