- 戦術カタールがどんな考え方なのか知りたい。
- 日本対ブラジル戦のポイントをつかみたい。
- この戦い方がなぜ注目されているのか理由を知りたい。
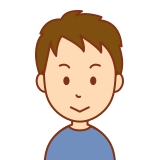
この記事を読むことで、
・用語の意味と成り立ちが分かります。
・日本対ブラジル戦の流れと見どころを理解できます。
・今後の日本代表を見るときのチェックポイントがつかめます。
日本対ブラジルハイライト
10月14日の国際親善試合で、日本はブラジルに3対2で逆転勝ちしました。
前半は0対2でビハインドでしたが、後半に流れを引き寄せます。
52分に南野拓実選手が1点目を決め、60分前後に中村敬斗選手の同点弾。
71分には上田綺世選手のヘディングで勝ち越しに成功しました。
後半は前からの守備がかかり、ボールの奪い方と攻めの速さが一気に上がったのがポイントです。
交代選手の走力と、セットプレーの精度も勝利を後押ししました。
戦術カタールとは
戦術カタールは、日本代表の試合の進め方を分かりやすく呼んだニックネームです。
前半はムリをせずに守りを整え、体力と集中を温存します。
後半はラインを押し上げ、前からボールを奪いにいく強い守備と、少ないパス本数でフィニッシュまで行く速い攻撃に切り替えます。
守備では、相手のセンターバック同士の横パスやキーパーへの戻しなど合図に合わせて一気にプレスをかけます。
攻撃では、サイドで相手を引きつけ、内側のレーンへの縦パスや裏抜けで決定機を作ります。
60分前後の交代カードで走力と強度を上げるのも大事な要素です。
この呼び名は正式な戦術名ではなく、みんなが使う分かりやすい言い方です。
なぜ広まった?
きっかけはエースの堂安律選手の発言です。
堂安選手が、後半にギアを上げる設計を“戦術カタール”と表現したことで、一気に注目が集まりました。
ブラジル戦で実際に、前半は我慢し、後半にプレス強度と攻撃テンポを上げて逆転したため、言葉と試合内容がピッタリ一致しました。(カタールW杯(2022)での成功体験が元ネタ)
メディアやSNSでも取り上げられ、ファンのあいだで広く使われるようになりました。
ポイントはフォーメーション名ではなく、試合の進め方をまとめて呼んでいるという点です。
まとめ
戦術カタールは、前半はリスクを抑え、後半で強く速くする日本代表のゲームモデルを分かりやすく言い表した言葉です。
ブラジル戦の逆転劇で説得力が増し、堂安選手の言葉を通じて広まりました。
試合を見るときは「いつ強度を上げるのか」「どこでボールを奪うのか」「交代で何が変わるのか」に注目すると、より深く楽しめます。
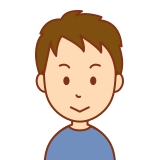
堂安選手の発言はたびたび話題になりますね。
言い得て妙な、言葉のチョイスにセンスを感じますね。

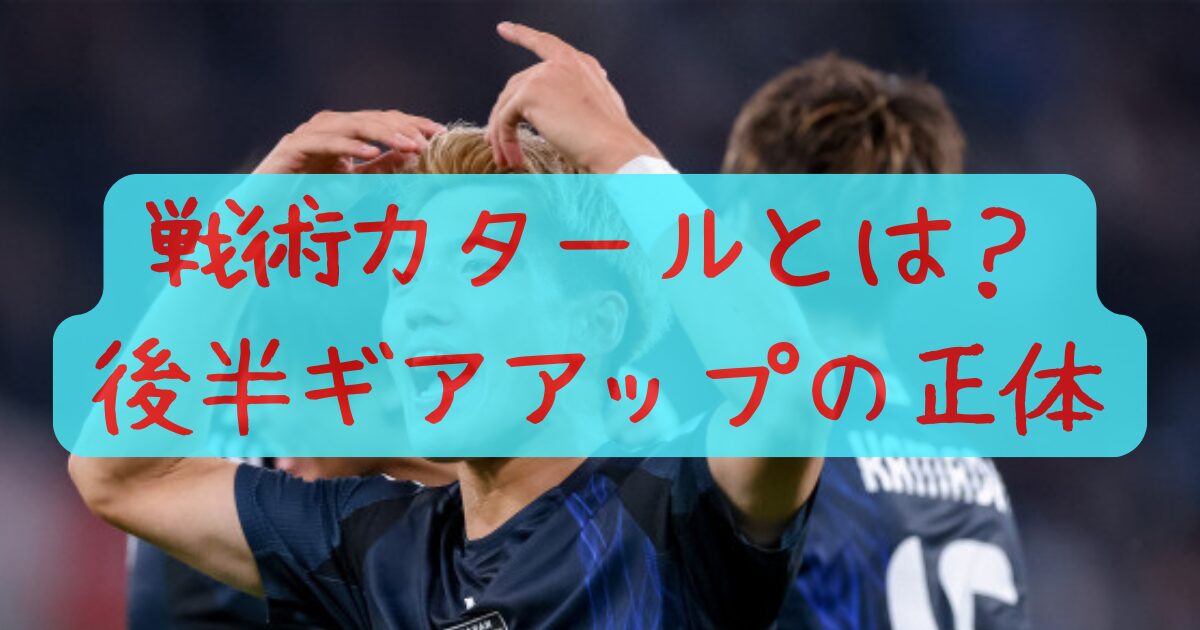



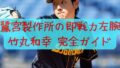
コメント